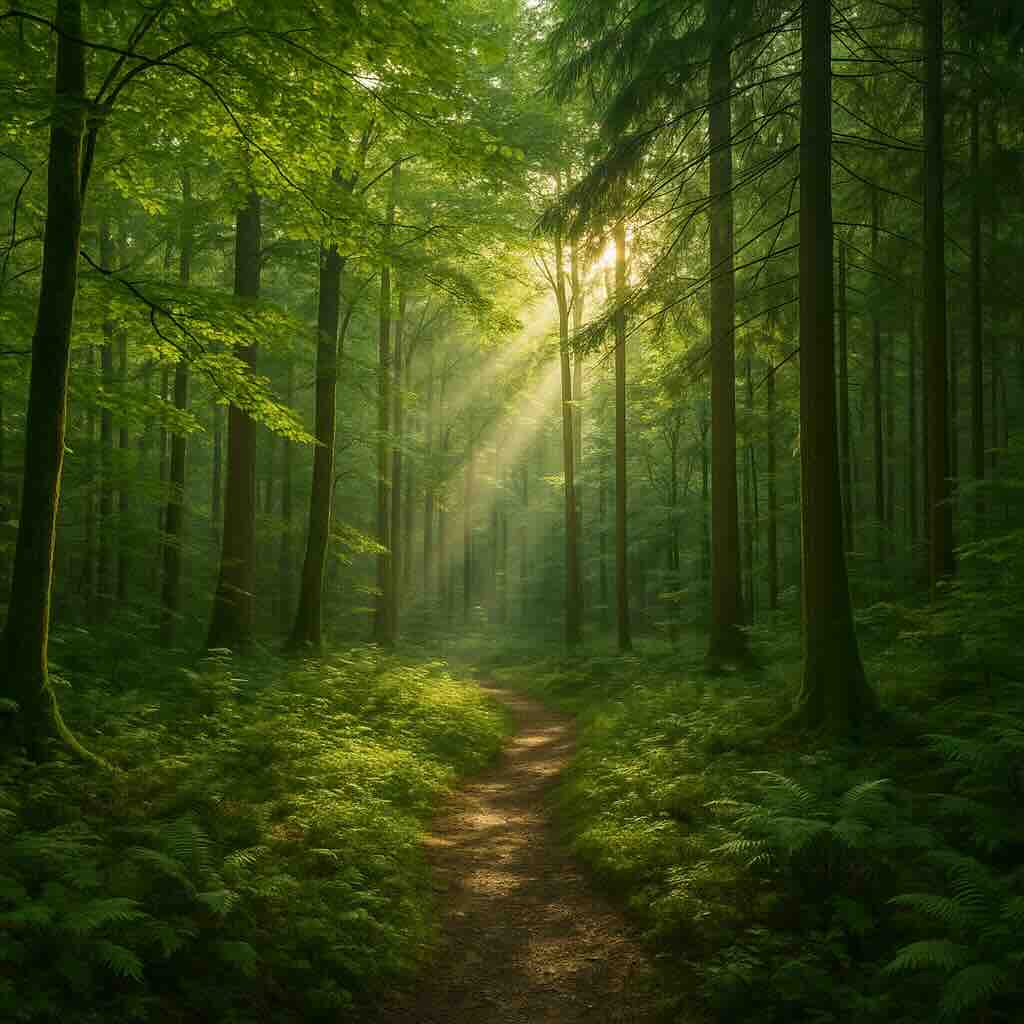樹木を知ろう
”自然の中が好き”についての随想
樹木を20年間見つめてきた代表の樹木への考え方、自然との関わり方を個人の視点で綴ります。
コラム・随想第3回目は、「自然の中が好き」である理由を考察します。
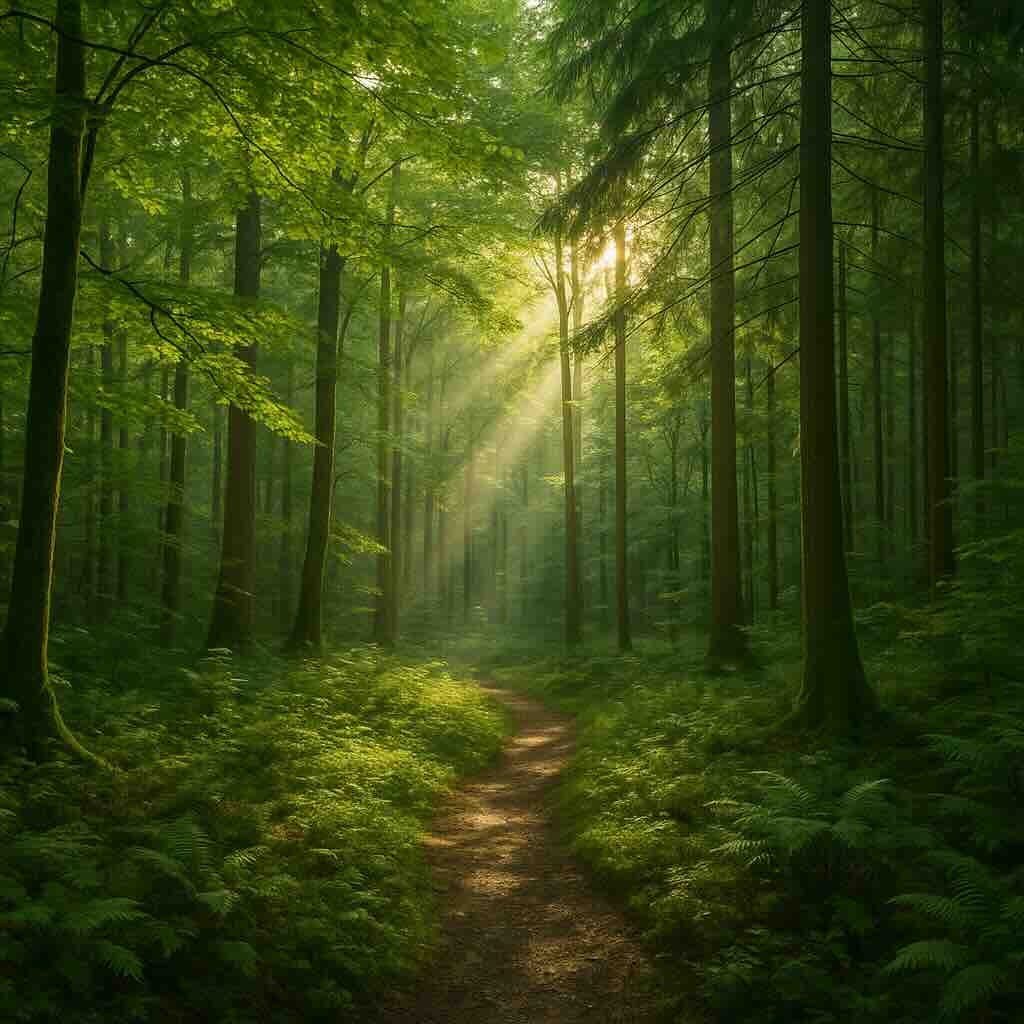
緑色について
緑色を見ると、なぜかほっとする。忙しい日々の中で、ふと目に入る木々の緑や草の色に、私たちは何故か安堵する。この不思議な感情にはきっと理由がある。そもそも人は緑色に癒されるようにできているのではないだろうか。
緑色は目にやさしい色である。可視光の波長としてもちょうど中間にあり、網膜への刺激が少ない。そのため、長く見ていても疲れにくく、自然と身体がリラックスする。
緑色の影響として最も大きなものは「緑色=自然」という連想だろう。木々、草原、森、そういった緑色から連想される自然の風景には、安定した情緒や安心感が常にある。特に都市に暮らす現代人にとって、緑色は無意識のうちに「休息できる場所や心の安寧」などの象徴となっているのではないだろうか。
人にはもともと、自然とつながっていたいという本能があると感じる。この本能については「バイオフィリア」と呼ばれており、1984年にアメリカの生物学者 エドワード・O・ウィルソン(E.O. Wilson) によって提唱された造語である。人類は99%以上の歴史を自然環境の中で暮らしてきた。安全な水場、食料、避難場所、生存のヒントはすべて“自然の中”にあったことで、緑色=自然=安心な場所、のように本能に刻まれたのかもしれない。「バイオフィリア」という言葉自体は「人間には生まれつき、自然や生命あるものとつながりたいという本能的欲求が備わっている」という概念である。
緑色には記憶を呼び起こす作用もある。森で遊んだ子ども時代や、旅行先の風景、草の匂いや木漏れ陽の光。そういった記憶が重なって、緑はただの色ではなく、記憶の風景を呼び覚ますトリガー的な働きがあるように感じる。
文化の中でも、緑色は調和や平和を象徴する色として親しまれており、青信号の進行サインや、病院や学校の内装にもよく使われるのは、無意識に安心をもたらす色だからである。
緑色を見るとほっとする。その感覚には、単に可視光としての色を超えた深い理由があるのかもしれない。

フィトンチッドとマイナスイオン
森を歩いていると、なんとも言えない爽やかさを感じることがある。深呼吸したくなるようなあの空気。あの心地よさの正体、それは「フィトンチッド」と「マイナスイオン」である。
フィトンチッドとは、植物が自分自身を病害虫から守るために放つ揮発性の成分のことである。1928年、ロシアの生化学者トーキン博士が発見し、ギリシャ語の「植物(phyton)」と「殺す(cide)」を合わせて名付けられた。
ヒノキやスギ、モミなどの針葉樹は特にフィトンチッドを多く放出することで知られており、空気中の菌やカビを抑えたりする働きがある。このフィトンチッド、人体に対しては自律神経を安定させたりする作用があるとされている。また、森林浴のリラックス効果の中心にあるのもまさにこの成分なのである。
一方、マイナスイオンという言葉は、少し前にブームとなったこともあり、どこか“健康によさそう”というイメージがある。空気中の微粒子(分子)に電子がくっついた状態のマイナスイオンは、実際に滝や渓流のそばなどでは、大量に存在している。
森林では、植物の蒸散や葉の表面からもマイナスイオンが発生していると考えられており、効果については、空気を清浄にしたり、脳波を安定させたり、呼吸を深くしてくれるといった報告がある。なぜそうなるのかの原理については、分子レベルで帯電してストレス状態になった神経の先から、電気を逃すアーシングのような効果であろうが、これらはあくまで補助的な効果と考えるべきである。いずれにしても、フィトンチッドとマイナスイオン、そのどちらも自然の中に溶け込んでおり、私たちが森の中で感じる“あの気持ちよさ”の正体の一部となっていることは確かなのである。
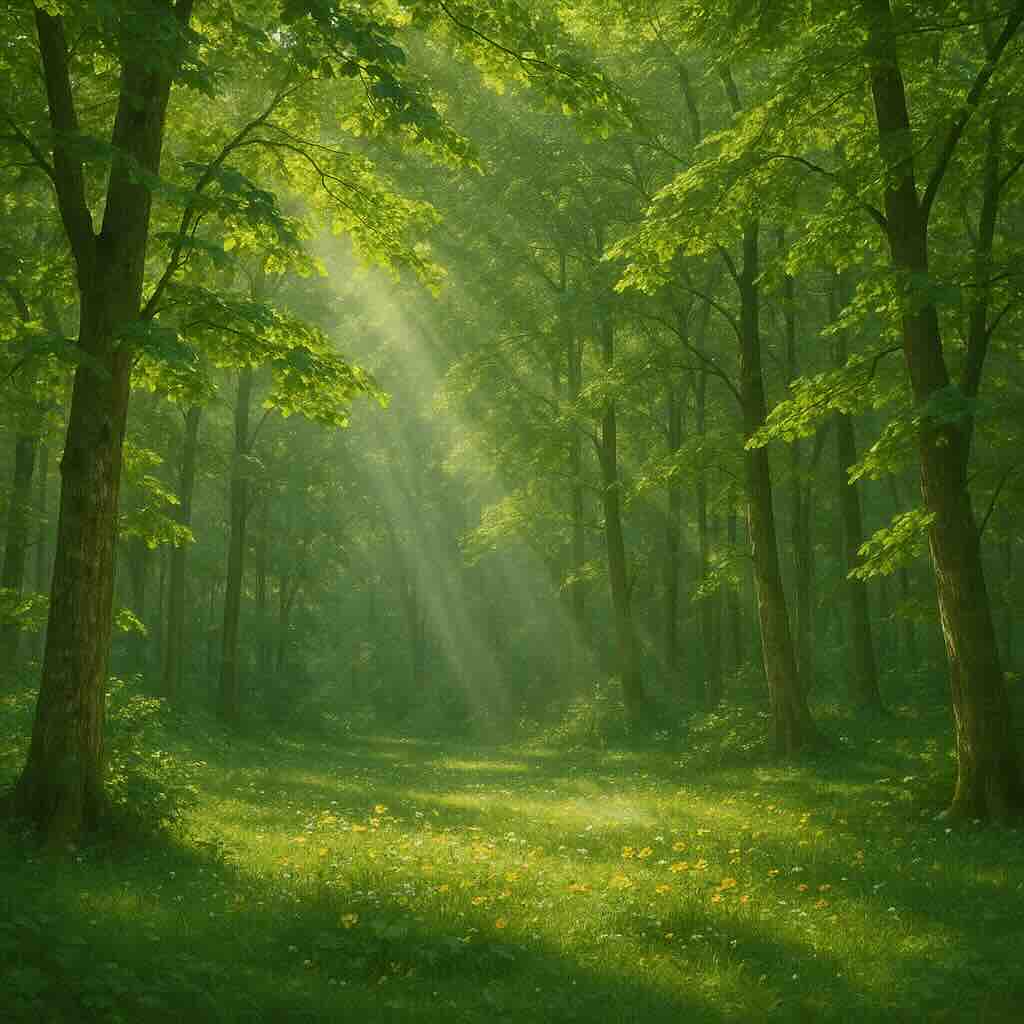
匂い・音・光
森の中を歩いていると、大抵の人が”心の静寂”を感じるのではないだろうか。
木々の間からこぼれる陽射し”木洩れ陽”は、直射日光とは違って、葉を通して拡散され、柔らかくゆらゆらと瞼をくすぐる。その光は風に揺れ、かたちを変えながら木の葉の影を地面に映し出す。この揺れる光のリズムは人の感覚をその光に集中させる。その集中が心の静寂の状態を生むと私は考える。時間や季節とともに変化する木漏れ日は、飽きることなくどんな時でも心の静寂をもたらしてくれるのである。
森には音がある。雑音とも機械音とも違うが一定のリズムのある音、それは風のざわめき、鳥の声、小川のせせらぎ、葉同士が擦れ合う音、虫の羽音といった音である。これらの音は「1/fゆらぎ」と呼ばれ、不規則(ランダム)であるが全体としては調和の取れたリズムなのである。これは人間の心拍や脳波と共鳴しやすいらしく、森の音を聴き続けると心が落ち着いていくのだそうだ。自然の音は、聴覚を通じて内側のリズムを整えてくれる“聴く森林浴”と言えるのではないだろうか。
森には独特な香りがある。ヒノキやスギなどが放つフィトンチッドのわずなか芳香や、植物の蒸散や微生物の活動により、森の空気にはわずかな湿気と冷たさが、独特の匂いを醸し出している。森の香りは、単なる嗅覚刺激ではなく、私たちがかつて土に触れた記憶や木に登った記憶、そこに同時にあった感情なども呼び起こすトリガーにもなるのだ。

虫・鳥・動物
森に入ると、そこにはさまざまな命の気配を感じることができる。虫の羽音、鳥の羽ばたき、動物たちの気配。これらの存在は、単に自然の一部というだけでなく、人の心に何らかの形で作用すると私は考える。
たとえば、小鳥が枝にとまりこちらを見つめるとき、人はその視線の存在に気づき、「私は見られている」という感覚になる。その感覚は、鳥と自分がお互いに観察し合うことで、自分と自然は関係性があると無意識に知るのである。
また、生き物の気配は、私たちの記憶と深く結びついているように感じる。例えば、森の中で蝶を見たときに、子どものころの夏休み、虫取り網に虫籠、蝶を追うことに夢中になった時間、キャンプで食べたカレーの味、夜に揺れる炎、などなど。そんな記憶が一気に蘇ることがある。これは五感が記憶を呼び起こす「プルースト効果」にも通じる現象であるが、森には五感と記憶を結びつける効果もあるのではないだろうか。
自然の中にいると、「なにかがいる」という感覚が常にある。それは人ではないけれど、確かに“生きているものたち”の気配である。その気配は、ただそこにあるだけで、私たちの心に、自然と共存しているという感覚を残し、虫や鳥や動物たちは、言葉を持たないセラピストのように人の精神に作用するのである。

紅葉する木々
秋になると、木の葉が赤や黄色に色づく「紅葉」。これは、木が冬の寒さに備えて葉を落とす準備をしているサインである。
葉の内部には、もともと三つの色素がある。緑のクロロフィル(光合成の主役)、黄色や橙のカロテノイド(実は夏の間も存在している)、赤や紫のアントシアニン(秋に新たに生成される)である。
夏の間はクロロフィルが豊富に存在するため葉は緑に見えるが、気温の低下や日照時間の短縮によってクロロフィルが分解され、カロテノイドが目立って黄色に変化する。さらに冷え込みが強まると、アントシアニンが生成されて赤みが加わる。
紅葉の美しさは天気にも大きく左右される。その年ごとに紅葉の色づき具合が異なるのは、気温、日照、湿度、降雨量といった気象条件のわずかな違いによるものである。昼が晴れて夜に冷え込み、適度な湿度のある秋は、特に色が鮮やかになる。日中の光で葉に糖分が蓄積され、夜間の冷え込みによってアントシアニンの生成が促されるため、赤みがより強く現れるのである。逆に、秋の初めに強い霜が降りたり、長雨や台風の影響で葉が傷んだ年は、紅葉が早く終わったり、色がくすんだりすることもある。
木の種類によって色づきにも違いがある。アントシアニンが多く含まれるモミジは赤く、カロテノイドが主役のイチョウは黄色に、両方が混ざるカエデは赤や橙、黄色が重なって色づくこともある。
やがて葉の付け根には「離層」と呼ばれる切り離しのための層が形成され、水や栄養の通り道が閉ざされる。こうして色づいた葉はその役目を終え、落葉が始まるのである。
紅葉の美しさは、長く続かない。それが儚さや郷愁を呼び起こすトリガーになるのである。紅葉に嫌な思い出でもない限り、人は紅葉が大好きなはずである。晩秋、木々の静かな生命の営みの最後は、「木の葉時雨」で幕を閉じるのである。

厳しい寒さと芽吹き
しんと静まり返る森。耳を澄ます。なにも聞こえない。沈黙する木々。たまに遠くで雪が落ちる音が聞こえる、風に舞った雪がさらさら音を立てている。
厳しい寒さにさらされる森は、生命の動きを止めたかのように見えるだろう。しかし、それは終わりではなく、始まりの準備である。木々は春の芽吹きのためにエネルギーを蓄え、根を深く張る。かつて、人もまた寒さにじっと耐え、静かに春を待っていたのである。冬の森が教えてくれるのは、困難は必ず終わるという希望と季節は巡ることへの喜びである。
やがて訪れる芽吹きの季節、雪解けとともに現れる若葉の色は、寒さが厳しかったほどに鮮やかに感じる。その新緑は、人の心に新たな希望のように映るのではないだろうか。厳しい冬は希望の資源となるのだ。
自然のリズムは循環である。朝が来て夜が来る。春が訪れて冬が巡る。人はその循環の中に身を委ねるとき、自分の記憶も人生も、自然と共に巡っていることに気づき「自然が好きだ」と感じるのかもしれない。